「ちょっと最近、物忘れが多くなってきたかも…」
そんな母のひとことから始まった、我が家の介護ストーリー。
もの忘れ外来に行ったり、転倒で頭を打ったり、なぜかちょっとクセの強いセンター長と出会ったり(笑)
最終的には「介護認定を受けておいて本当によかった」と思えた私の体験をお話します。
🧠母の変化に気づいた日──もの忘れ外来から介護認定へ
🍵「最近、物忘れが多くてね…」母のつぶやきから
今からおよそ5年前、母が80歳か81歳の頃のことです。
当時の母は、「最近、物忘れが多くなったんよね」と自分でも気にしていました。
ある日、近所の人が
「私も物忘れが多くて、かかりつけの内科で相談したら薬を出してもらえたよ」
と話してくれたのを聞いて、母は
「私も病院で薬、もらってみようかな…」と、ぽつりとつぶやきました。
🏥かかりつけ医に相談。もの忘れ外来を紹介される
母は高血圧&血糖値高めのため、月に一度、近所の内科に通っていました。
その日は私が付き添っていたので、診察時に先生に思い切って相談してみました。
「母が最近、物忘れを気にしていて…。もし薬があるなら、処方していただけませんか?」
先生は少し考えてからこう言いました。
「こちらで処方することもできますが、紹介状を書きますので、よければ“もの忘れ外来”を受けてみませんか?」
母に「どうする?行ってみる?」と聞くと、少し考えたあと「行ってみようかね」と答えたので、紹介状をいただいて受診することになりました。
🧪検査の結果:「認知症ではないけれど…」
もの忘れ外来では、MRIやCT、問診、記憶力テストなどが行われました。
診断の結果は、
「脳の萎縮は多少あるものの、海馬の萎縮が目立つわけではなく、現時点では認知症とは診断できません」
とのことでした。
ただ、同年代と比べて脳の萎縮が平均より進んでいるという説明があり、不安は残ったものの、薬の処方もなく、
「散歩などの有酸素運動で脳を刺激しながら生活習慣に気をつけてください」
というアドバイスを受け、またいつもの日常に戻っていきました。
🚶転倒、ケガ、そして…認知症の診断
🚨頭を打った日。再び病院へ
それから約1年後、転倒やケガが目立つようになってきました。
ある日、母が軒下で転んでコンクリートで頭を打ち、額から血が出ていたのです。
その日私はリモートワークだったため、すぐに脳神経外科へ連れて行き、幸い外傷の処置だけで済みましたが、先生からは
「脳が萎縮していますね。病院で検査したことはありますか?」と聞かれました。
1年前に“もの忘れ外来”で診てもらったことを伝えると、先生はやや不満そうに「うーん、見解の違いかな…」とひとこと。
「見解の違いということは、もしかしたら、あの時点でも診断がついていたのかも…」と後悔の気持ちも湧いてきました。
🧾アルツハイマー型認知症と診断される
一ヶ月ほどケガの治療に通って怪我が治ったあと、再度検査を受けた結果──
「アルツハイマー型認知症(初期〜中期)」と診断されました。
記憶力テストのグラフを見ながら、先生は丁寧に説明してくれました。
- 血流を良くする薬
- 脳に刺激を与える薬
- 骨を強くする薬
薬の服用によって、記憶力の低下が緩やかになる可能性があるとのことでした。
それから2週間ごとの通院が始まり、1年ほどたつ頃には月1回のペースで通院。
📞介護認定の申請と古狸センター長!?
🧓地域包括支援センターとのやり取り
その後先生から「介護認定を受けておいたほうがいいですよ」と言われ、市役所に問い合わせたところ、地域包括支援センターを紹介されました。
電話をすると、センター長と名乗る男性職員が訪問して面談してくれることになりました。
しかしこの方、最初は頼もしく見えたものの──
この古狸(※私がセンター長に付けたあだ名)とのやりとりは、今でも忘れられません。
「お母さんは他の方に比べると元気な方ですよ。私が見る限りまだ介護サービスを受けるのは早いと思います。申請したとしても認定は厳しいと思いますよ。それに申請すると今度は市役所の職員と面談がありますので、厳しい質問をされて嫌な思いをするかもしれませんけど…申請されますか?」
と、やんわり「やめといたほうがいいよ」と言わんばかりの口調で言われ、私は申請をいったん取りやめてしまいました。
そのときの私は、「母はまだ元気な方なの?」「申請ってそんな厳しいもの?」「なんだか先生の言うことと話が違うな・・・」と思い、「そこまで脅してくるなら申請しなくてもいいか・・・」と、あっさり引き下がってしまいました。
💬主治医の一言で再び動き出す
翌月の診察で先生に報告すると、 「断られても申請してください。介護保険料だって払ってるんですから介護サービスを使わないと」とビシッと一言。
その言葉に背中を押され、また勇気を出して古狸センター長に連絡することに。
再訪した古狸センター長は、「申請するからには認定してもらわないといけませんから、困っていることをしっかり伝えてくださいね」と、どこか腑に落ちない態度。
自分の評価ばかり気にしているようで、私の心はモヤモヤ・・・
「この古狸、一体誰の味方?この前と言ってることが全然違うじゃん!」
と内心はツッコミつつ、母の物忘れや困りごとを説明しました。
👩役所職員との面談と認定結果
その後、市の職員(女性)と古狸センター長が一緒に再訪。
役所の職員さんはとても感じが良く、母も安心して面談に応じていました。
(厳しい質問や嫌な印象はありませんでした。)
1ヶ月後、届いた結果は「要介護1」。
すぐに古狸センター長に報告すると
「いや〜良かったですね!私は要支援だと思ってましたよ、あははは(笑)」なんて言われ
心の中で、
“いやいや、あの時の脅しは何だったのさ?よく言うよ、まったく・・・”と軽く突っ込みをいれました。
📝補足:介護認定の流れと「要介護1」って?
介護認定は、以下のような流れで進みます。
- 地域包括支援センターや市役所で申請
- 市の調査員が自宅で面談・調査
- 主治医の意見書とあわせて審査会が判定
- 約1ヶ月で結果通知(要支援〜要介護の7段階)
「要介護1」は、日常生活の一部に介助が必要な状態。
(例:入浴や排泄、外出などに少しサポートが必要)
この認定によって、介護保険サービスが使えるようになり、古狸センター長からケアマネジャーさんの事業所を紹介されました。
✅私がこの体験から学んだこと
今振り返ってみると、主治医の先生が「断られても申請してください」と言ってくれたことが、本当にありがたかったと思います。
あのとき、古狸センター長の言葉にまんまと引っかかって、申請をやめてしまっていたら──と思うとゾッとします。(クワバラクワバラ)
介護認定は、申請するまでにも関門があるんだな…と実感しました。そして最終的に認定を左右するのは、包括支援や市の面談ではなく、主治医の意見書の影響が大きいということも身をもって知りました。
だからこそ、もし今この記事を読んでいる方が、主治医から「介護認定を受けてみては?」と勧められているなら、
迷わず申請してほしいです。
介護サービスを利用できるかどうかは、その一歩を踏み出すかどうかにかかっています──私のように遠回りしないで済みますように・・・
それともうひとつ── 最初に市役所に行ったとき、私は当然のように窓口で申請するものだと思っていましたが、「地域包括支援センターを通して申請してください」と案内され窓口での申請はやんわりと拒否されました。
当時は「そのほうがスムーズなんだな」と軽く受け止めていましたが、今振り返ると、あれはもしかして“申請のハードルを一段高くする仕組み”だったのかも…?と、少しだけ“制度の闇”を感じてしまいました。
もちろん、すべての地域や担当者がそうとは限りません。でも、誰かの主観や立場で「申請にブレーキをかけるような構造」があるのだとしたら、それはやっぱり残念なことですよね。
この続きは──「デイサービス拒否」のお話へとつながります。
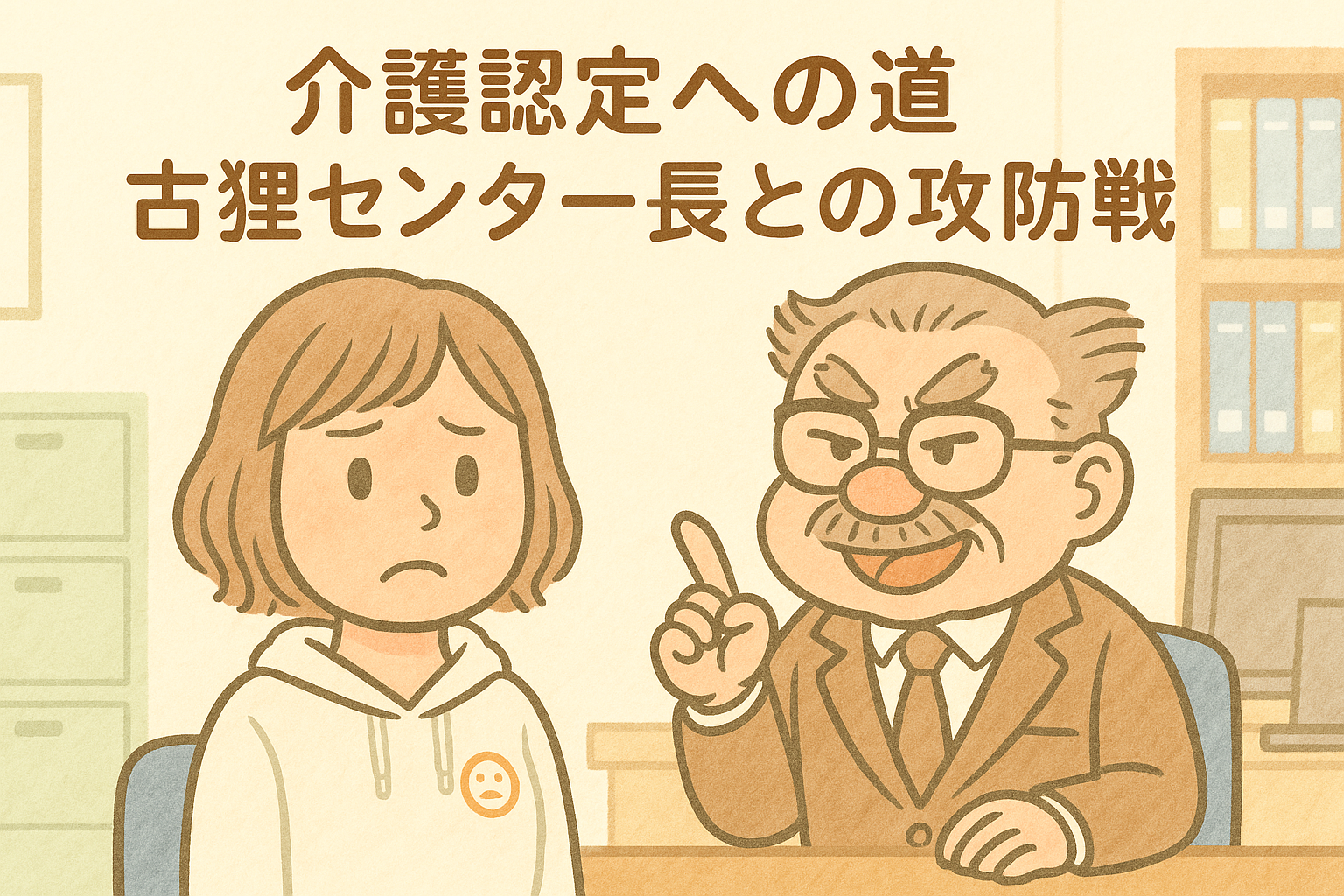


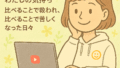
コメント